|
この資料は海外安全対策連絡協議会(2007年4月27日)において仲本医務官により行われた講演内容の抜粋です。
海外在留邦人・海外渡航者の状況
- 2005年10月現在、在留邦人数は、1,012,547人
- 2005年の海外渡航者数は、17,403,565人
- 海外勤務健康管理センターデータ
海外赴任者の39%が神経症圏、20.9%が抑うつ状態圏
- 海外邦人援護統計2005年(外務省)19,503人
疾病が930人、精神障害が288人
-
精神障害の傾向
-
年齢別では20代〜30代
北米・アジア
女性>男性、短期滞在>在留邦人
自殺死リスク=交通事故死リスク (毎年50人前後)
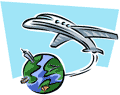 在留邦人数、海外渡航者数(旅行者数)は年々増加しています。海外赴任者に神経症、うつ病の予備軍が多い事がわかります。精神障害書の傾向を示しています。海外で自殺をされる方は交通事故で亡くなる方とほぼ等しい状況です。 在留邦人数、海外渡航者数(旅行者数)は年々増加しています。海外赴任者に神経症、うつ病の予備軍が多い事がわかります。精神障害書の傾向を示しています。海外で自殺をされる方は交通事故で亡くなる方とほぼ等しい状況です。
在 NY 総、邦人援護案件(2005年)
邦人援護案件(2005年)
| 事故・災害 |
21件 |
| 犯罪加害 |
3件 |
| 犯罪被害 |
109件 |
| その他 |
351件(うち精神障害36件) |
当館の邦人援護担当官が精神障害援護案件を扱う事例は年間36例でした。
企業のリスク管理、安全配慮義務
- 加古川労基署事件(平成8年4月)
- 新入社員24歳のインド・タールサイト出張中の自殺
- 現地でのトラブルから反応性うつ病に罹患し自殺した
- 労災保険の適応が裁判上初めて認められた事例
- 判決理由
- 海外生活でのストレスに加え、仕事上の困難が加わると、心因性精神障害の発生の危険性が高まる
- 新人には過酷な勤務、相談相手のなさ、ビジネス上の契約履行に対する現地サイドのルーズさ
海外で起きた自殺が労災として認められた初めてのケースです。タールサイトはムンバイの南130kmの田舎町です。判決では、彼の海外勤務には、定型的に反応性精神障害を惹き起こす準備状況となるべき要素があり、その上に宿舎問題という強い精神的負荷が加わった、即ち業務起因性であるとしました。この判決から考えられる事は、海外勤務者、そしてそのご家族に対して、安全衛生や健康管理、そしてメンタルヘルスに配慮した職場環境の整備が企業に求められる、という事になります。

メンタルヘルスケアを推進する根拠
 健康の保持増進活動 健康の保持増進活動- 心と体の相関
 労働生活の質の向上と職場の活力の向上 労働生活の質の向上と職場の活力の向上- 心の健康状態と経営成果との明確な相関関係
 リスクマネジメント リスクマネジメント- 事故、自殺の未然防止
 企業がメンタルヘルスを推進しなければならない根拠をまとめています。まずは、健康の保持増進活動という面があります。そして、欧米での研究によれば、心の健康状態は、経営成果と明確な相関関係がある、つまり、社員の心が健康な会社は売り上げも良いと言われています。さらに、労災の件で示した、企業のリスクマネージメントという面があります。 企業がメンタルヘルスを推進しなければならない根拠をまとめています。まずは、健康の保持増進活動という面があります。そして、欧米での研究によれば、心の健康状態は、経営成果と明確な相関関係がある、つまり、社員の心が健康な会社は売り上げも良いと言われています。さらに、労災の件で示した、企業のリスクマネージメントという面があります。
仕事のストレスに関連する疾病
-
重傷度が高く、仕事のストレスと関連が比較的強いもの
-
- 虚血性疾患
- 脳血管疾患
- 自殺
- 仕事上の事故災害
- 交通事故
-
頻度が高く、仕事および生活の質への影響が大きく、仕事のストレスと関連があるもの
-
- 高血圧
- 不整脈
- 肥満
- 高脂血症
- 糖尿病
- 脂肪肝
- 胃・十二指腸潰瘍
- アルコール関連障害
- 腰痛・頸肩腕痛
- うつ病
鬱病、自殺ばかりではなく、仕事のストレスと関連がある病気を挙げています。重傷度が高いものとしては、虚血性疾患(狭心症や心筋梗塞)、脳血管疾患(脳梗塞など)があります。頻度が高く、仕事や生活の質への影響が大きいものとしては、高血圧、不整脈、肥満、高脂血症、糖尿病、脂肪肝等の生活習慣病、胃・十二指腸潰瘍、アルコール関連傷害、腰痛、肩こりなどがあります。

海外派遣労働者の精神的健康と関連性の高い要因
- 風俗習慣の違いによる不自由さ
- 医師の指示理解能力のなさ
- 現地人上司との関係の悪さ
- 年休消化日数
- 運動習慣
- 喫煙習慣
- 家族交流のなさ
- 相談者の不在
- 単身派遣
- 現地交流のなさ
産業衛生学雑誌より引用
海外派遣されている方々にとって、メンタルヘルス上問題、精神的な健康との関連が高いと考えられる要因について列挙しています。
- 1、風俗習慣の違いによる不自由さです。異文化で仕事をされている皆様は既に痛感されていると思います。
- 2番目には医療の問題が上がっています。言葉がどんなに堪能な方でも、現地の医師が何を言っているのかわからない、理解できないという事はよくあります。
- 3番目には、現地人上司との関係の悪さが上がっています。欧米で働かれる場合には頻度の多い問題になっています。
- 4、年休消化が少ない方は、精神的不健康になりやすいという事がわかっています。
- 5、運動週間の無い方、仕事ばかりしている方は、精神的不健康になりやすい。そして喫煙習慣のある方もメンタルヘルス上問題が多い。
- 7番目ですが、家族との交流の少ない方は、精神的に不健康な状態にある、という事もわかっています。これは8番、9番とも関係しますが、単身赴任で、サポートしてくれる家族や相談者がいない場合に問題が起こりがちになります。
- そして、単身赴任であっても、地元でいろんな交流があれば良いのですが、仕事でのつき合いのみ、現地であまり交流をされていない方に、メンタルヘルス上の問題がおこりがちであるという事がわかっています。

海外生活、適応の過程
-
1.移住期(数週間から数ヶ月)
 精神的な問題は少ない 精神的な問題は少ない
-
2.不満期(数週間から数ヶ月以降)
 心身の不調を来しやすい 心身の不調を来しやすい
-
3.諦観期(数ヶ月から1年以降)
 肯定的な認識 肯定的な認識
-
4.適応期(1年以降)
 生活をエンジョイ 生活をエンジョイ
-
5.望郷期(2〜3年以降)
 メランコリックな気分 メランコリックな気分
海外の生活で精神面で適応していく段階は5段階に分けられます。
移住期ですが、挨拶回りと生活の設営に追われる時期です。この作業に必死で精神的な問題は起こりません。見かけ上は適応しているように見えます。しかし、この時期にがんばり過ぎると後で心身の疲労をひきずり事になります。この時期こそ余裕をもってマイペースで進めなければなりません。
不満期ですが、生活の設営が終わり、ほっと一息つく時期です。その一方現地、赴任地の欠点やストレス源が眼に付いてきます。この時期に心身の不調や精神障害による自殺といった問題がおこりがちです。辛いときは十分に休養をとる必要があります。
諦観期、諦めの時期ですね。赴任地の良いところも悪いところも概ね肯定的に認識できるようになります。心理的にもおちつきます。
適応期。現地に無理なくとけ込み、生活をエンジョイできる時期です。普通の方は1年はかかります。
最後の望郷期。2〜3年以降になると、赴任地の刺激に慣れてくると日本が懐かしくメランコリックな気分になります。引っ越し準備や日本再適応への不安が引き金になり心身に不調を来す事もあります。

メンタルヘルスケアの進め方
メンタルヘルスケアの進め方
| セルフケア |
本人のストレスへの気づき、ストレスへの対処 |
| ラインによるケア |
管理者による職場環境の改善、個別の相談対応 |
| 事業内産業保険スタッフによるケア |
産業医、衛生管理者などによる職場環境の改善、個別相談 |
| 事業外資源によるケア |
事業所外の機関や専門家による直接、支援サービス |
企業において、メンタルヘルスケアをどう進めていくか、という事ですが、4つのケアという事が提唱されています。
1番目はセルフケア。まずは自分自身がストレスを気づき、そしてそれを対処する方法を知っているという事。
2番目は、ラインによるケアです。これは管理監督者が行うもので、職場環境を改善し、個別の相談対応を行う、というものです。
そしてさらに事業内産業スタッフ、産業医などによるケア、そして事業外の専門家による支援サービスというものも利用する必要があります。
セルフケア
セルフケアですが。今はインターネットでも自己診断できるストレスチェックというものもありますのでご利用ください。対処方法としては、みなさんそれぞれかと思います。そして何よりも、ちょっとおかしいなと思ったら遠慮無く専門家に相談する、という事が重要です

ラインによるケア・気づきのポイント
- 職場生活
-
- 遅刻・早退が多い
- 休みの連絡がない
- ミスが目立つ
- 能率が悪くなる
- 思考、判断力の低下
- 会議で攻撃的になる
- 日常生活
-
- 気分の変容が大きい
- 体重の増減が目立つ
- 服装が乱れ、不潔になる
- 元気がない、表情が乏しい
- 口数が少ない、多弁になる
- 浪費をする
- 飲酒量、タバコの増加
- 今までの趣味に興味がなくなる
部下の異常への気づきのポイントをあげてみます。
職場生活においての異常ですが、遅刻・早退が多い、休んだが連絡がない、そしてミスが目立つようになった、以前に比べて能率が悪くなった、判断力が低下した。そして会議で攻撃的になるという異常を呈する方もいます。
日常生活ですが、これについては奥様が同行されていれば、夫人を通して入ってくる情報になるかと思いますが、気分が変わりやすい、体重が増えたり減ったりする、服装が乱れて不潔になっている、表情が乏しくなっている、口数が少ない、逆に妙に多弁になる場合もあります。浪費するようになる、無駄な買い物をするようになるという事もあります。酒やタバコが多くなるというのも重要なサインです。そして、今までゴルフや麻雀が誰よりも好きだったのに、そうした誘いに乗らなくなる、というのも異常のサインです。こうした部下のサインを見た場合には、直ぐに個別相談をしてみる必要があります。

ラインによるケア・定期的チェック項目
- 原因のはっきりしない体調不良はないか?
- 食べられているか?
- 眠れているか?
- 酒量が急に増えていないか?
- 気分や言動が不安定になっていないか?
- 仕事はある程度こなせているか?

めったに会わない社員、部下の異常を定期的にチェックする質問項目という物もあります。本社から産業医や人事担当者がするべき質問ですが、この6つの質問を定期的にする事で、メンタルヘルスの状態を大まかに把握する事が可能です。
問題があった場合の対応
問題があった場合の対応
| 重傷度 |
症状 |
対応方法 |
| 軽症 |
軽い不眠、軽度の体調不良、自己回復力あり |
休暇を取らせる。必要に応じて現地での治療 |
| 中等症、重症 |
業務能力の著明な低下、顕著な体調不良、逃避願望、希死念慮、単身 |
一時帰国させる。精神的混乱が重篤な場合には、地元専門医療機関を至急受診させる |
 軽症の場合には、休暇をとらせるとか、現地の医療機関に対応可能な場合もあるかと思います。中等症、重症な場合、具体的には、業務能力が極端に落ちていたり、ここからいなくなりたい、といった逃避願望やさらに自殺をほのめかすような事を話す場合には、特に危険です。単身の場合には、こういう状態では1日でも放っておいてはいけません。直ぐに人をつけて帰国させるか、地元でとりあえず入院させるという事が必要になります。何より自殺させない、という緊急避難を実施する必要があります。 軽症の場合には、休暇をとらせるとか、現地の医療機関に対応可能な場合もあるかと思います。中等症、重症な場合、具体的には、業務能力が極端に落ちていたり、ここからいなくなりたい、といった逃避願望やさらに自殺をほのめかすような事を話す場合には、特に危険です。単身の場合には、こういう状態では1日でも放っておいてはいけません。直ぐに人をつけて帰国させるか、地元でとりあえず入院させるという事が必要になります。何より自殺させない、という緊急避難を実施する必要があります。

夫人のメンタルヘルス上の問題
- 言葉の問題
- 子育ての問題(異文化の中での教育)
- 培ってきたキャリアの問題
- 赴任理由、アイデンティテイーの問題
- 使用人との問題(途上国)
- 現地邦人社会との問題(村社会)
- ストレス解消方法の問題
- 健康問題、更年期の問題
- サポート体制の問題(企業支援の有無)
- 夫との問題
海外は夫婦の絆の試験場
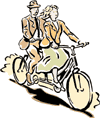 特に奥様・夫人について十分なケアを日本にいる時以上に気を遣わなければいけません。まずは、言葉、コミュニケーションの問題があります。英語も、全く苦手だと思っていらっしゃる方はもちろん、得意だと思っていた方も、現地で簡単な会話が聞き取れず、落ち込んでしまわれる方もいます。 特に奥様・夫人について十分なケアを日本にいる時以上に気を遣わなければいけません。まずは、言葉、コミュニケーションの問題があります。英語も、全く苦手だと思っていらっしゃる方はもちろん、得意だと思っていた方も、現地で簡単な会話が聞き取れず、落ち込んでしまわれる方もいます。
2番目ですが、お子様を同行されている場合には、子育てが一番の問題になるかと思います。教育の問題、子供が病気になった時、たいへん心配です。
3番目ですが、日本でばりばりに仕事をされていたが夫の赴任に伴い退職して付いてきた奥様方というケースも少なくないと思います。この「仕方なく、やむを得ずついてきた」、という気持ちが海外生活の場合に大きな問題になります。夫から十分な説明や相談がなかった場合に特にそうです。日本で積み重ねてきたキャリアが無駄になります。
4番目、海外で何をすれば良いのか、ご自身のアイデンティティーの喪失があります。ご主人の付属物のような存在が気にいらないという事は当然あるかと思います。そいう場合には、それ以外のご自分自身の赴任理由、海外在住理由を持つ必要があるかもしれません。
5番目に、途上国の場合には使用人さんとの問題があります。人を使うという事は、日本にいれば夢のような話ですが、これはこれで使い慣れていない我々にとっては大きなストレスになります。
6番目、コミュニケーションに問題はないはずの邦人社会とのつき合いがストレス源になる事も少なくありません。気が付いたら邦人社会の中で孤立している、という事があります。その他では、ストレス解消法の問題、ご自身の健康問題、更年期の体調不良なども大きな問題になります。
9番目ですが、ストレスというのは、それを減少させる要因があるかという事でもその大きさが変わってきます。すなわちサポート体制があるかどうかです。日本にいれば、何かストレスがたまるような事があっても、別のコミュニティーと関わる事でストレスを軽減する事ができますが、海外の場合そうはいきません。また、家族や友達などが近くにいて、話を聞いてくれたり、一緒に悩んでくれたりしてくれる事も難しい。そうなると一人で悩んでしまう、となります。
10番目、海外では、一番のサポーターになるべき人が夫だと思います。夫が妻の支えにならないと海外では生活できない、と言えます。海外は夫婦の絆が試される場所と言えます。

事業外資源、心の相談可能な施設、NY
NYの場合には、多くの専門家がいますので、ちょっとでもおかしいと思ったら気軽に相談するようにしましょう。
心の相談可能な施設のリストはこちらをクリックしてください。
まとめ

海外生活のメンタルヘルスにおいて重要な点をまとめると、休暇をとること、夫婦円満でいる事、この2点がたいへん重要だという事になります。

|

